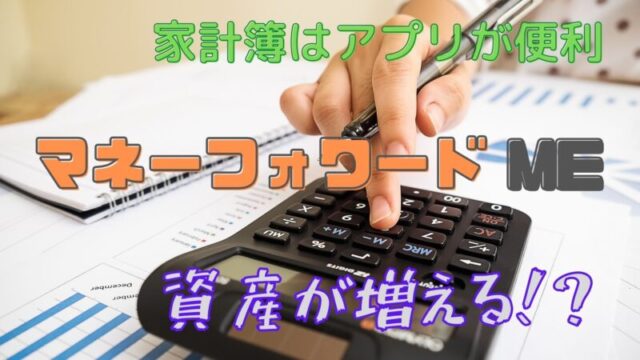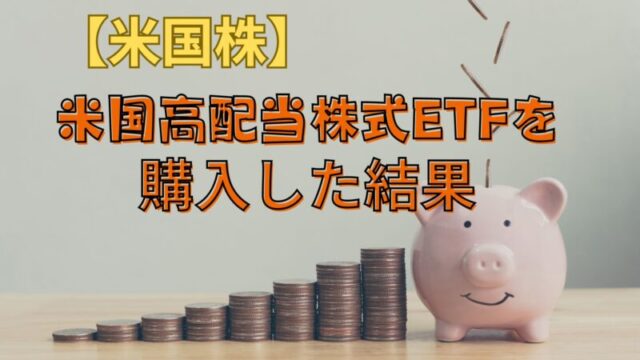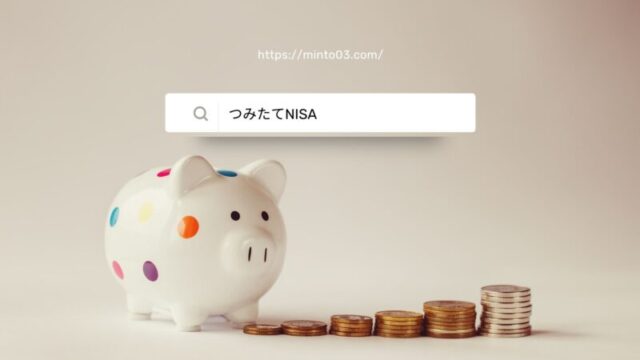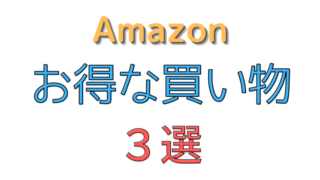iDeCo(イデコ)を始めてから1年、今の状況と感想

先日紹介した、つみたてNISA の1ヶ月後に始めた iDeCo(イデコ)。
iDeCoを始めてから1年過ぎた今の状況と感想です。
つみたてNISA は教育資金のため、iDeCoは老後資金のために始めました。
実際にiDeCoを始めて思ったことは、つみたてNISAより自由度が少なく、手続きが少し面倒で開設までに時間がかかる印象です。
しかし、つみたてNISA とは違うメリットがありますので、iDeCoを始めて良かったと思いました。
1年間継続してみた感想やメリットやデメリットなどを紹介していきますので、参考になれば嬉しいです。
iDeCo(イデコ)とは
iDeCoとは、個人型の確定拠出年金のことで、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。
自分で積立て
原則として毎月1回自動的に掛金の積立てられます。
拠出金額は月額5,000円か1,000円単位で設定できます。
職業等(会社員、公務員、自営業など)により、拠出限度額が違います。
積立てた掛金すべてが、所得控除の対象になります。
自分で運用
iDeCoを取り扱っている金融機関を選び、その金融機関で取り扱っている商品の中から選び運用します。
iDeCoで運用できる金融商品は大きく分けて2つ、定期預金と投資信託があります。
定期預金は元本確保型で、投資信託は株式、債権、REIT、などの種類があり、運用次第では元本が増えたり減ったりする元本変動型。
運用商品は掛金の範囲内で、複数の商品を組み合わせることもできます。
通常の金融商品の運用で得た利益には、20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの運用で得た利益すべてが非課税になります。
60歳以降から受け取り
原則60歳から一時金、または年金として受け取るか、もしくは一時金と年金を併用して受け取る方法があります。
一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の一定の非課税枠を使って受け取ります。
60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになります。
iDeCoを始めようと思ったきっかけ
老後資金の確保のため
少し遅いですが、40半ばを過ぎてやっと老後のことを考えるようになりました。
まだ小さい子供達もいるので教育資金の準備も必要ですが、また老後のことも考えないといけません。
先日紹介したつみたてNISAを始める頃、 iDeCoも調べていたので節税しながら老後の資産運用ができるiDeCoをやってみたいと思っていました。
それに、よく理解もせずに加入していた利率変動積立型終身保険が、あまりメリットがないことに気づいたので、解約して代わりにiDeCoを始めることにしました。
iDeCoの場合、原則60歳まで資産の引き出しができないので、老後資金の確保がほぼ確実にできそうだったからです。
節税できる
iDeCoのメリットの1つに、掛金が全額控除されることです。
生命保険料控除や年金保険料控除などでは、控除できる上限金額が決まっており、控除額も少ないです。
iDeCoの申込みから1年後までの流れ
iDeCoを取り扱っている金融機関はたくさんありますが、口座管理手数料の安いSBI証券を選びました。
SBI証券でiDeCoの申込み
2021年6月3日
楽天証券でつみたてNISAをしていたので、SBI証券のiDeCoを開設することにしました。
iDeCo口座のみの開設でも良かったのですが、後々のことを考えてSBI証券の証券口座も同時に申し込みました。
2021年6月19日
iDeCoのご案内の封書が届く
申込書に記入し、会社に確認の証明をもらって申込書を返送。
掛金は月々10,000円にしました。
2021年7月21日
メールにて口座振替の案内が届き、住信SBIネット銀行にて口座振替の登録をしました。
2021年8月26日
初めての口座振替。2ヶ月分の20,000円が引き落とされました。
iDeCoの商品選び
つみたてNISAでもでしたが、商品選びが一番悩みます。
しかも金融機関によりiDeCoの商品ラインナップも違います。
人それぞれ考え方が違いますが、僕の考え方は、つみたてNISAやiDeCoでは運用益が非課税なので、元本確保型ではなく、少しリスクをとってでも株式の投資信託を選んだほうがお得だと思います。
僕の場合、つみたてNISAで、楽天証券のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を選んでいるので、iDeCoでは全世界株式にしようと思っていました。
SBI証券のiDeCoの商品の中で、
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)と
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま)
の2つで悩みましたが、最終的に愛称:雪だるまと呼ばれている、SBI・全世界株式インデックス・ファンドに決めました。
掛け金は利率変動積立型終身保険に10,000円支払っていたので、とりあえず10,000円から初めてみました。
掛金変更してみた
少し余裕が出来たのと節税のため、掛金を限度額23,000円に変更することにしました。
掛金は1月~12月の間で一回変更できますが、掛金の変更はネットで完結せず、書類を取り寄せて変更しないといけません。
iDeCoは申込み時もそうでしたが、何かあるごとに書類で申請しないといけないので面倒です。
11月前半に掛金変更の書類を返送しましたが、掛金が変更になったのは翌年の2月からでした。
掛金の変更は時間を要するので、変更したい場合は早めに手続きがおすすめです。
SBI証券のiDeCoの各種申請・変更手続きの資料請求はこちら
運用実績
iDeCoを始めてから13ヶ月後の実績です。

2022年8月22日現在の資産残高は、233,527円です。
拠出金累計が221,000円なので、損益は12,527円のプラスになりました。
iDeCoの各種手数料も引かれた後の成績なので、損益率5.7%は良いと思います。
しかし、株価や為替など日々変動しているので、損益がマイナスになっていることもありました。
iDeCoのメリット
掛金が全額控除の対象
1年分の掛金が全額所得控除の対象になり、所得税や住民税が安くなります。
毎月23,000円積み立てているので、年間で276,000円。
仮に所得税10%、住民税10%の場合、年間で55,200円が節税できます。
運用益が非課税
預金や投資信託で運用し、利息や運用益がでた場合、通常20.315%の税金がかかりますが、iDeCoででた運用益は非課税になります。
資産が増える可能性がある
株式の投資信託では元本割れするリスクもありますが、長期運用で年利3~7%ぐらいになるそうです。
それに長期運用することで複利の力が働き、資産がどんどん増えていきます。
強制貯蓄ができる
iDeCoは60歳になるまで、掛金が引き出せません。
すぐに引き出せるようだと当てにして、途中で挫折しそうです。
そもそも老後資金を作る目的なので、60歳まで引き出せなくて当たり前だと思います。
スイッチング(預け替え)ができる
スイッチングとは、保有している資産の一部または全部を売却し、売却した金額ので別の商品を購入することです。
たとえば、投資信託で予想した利益に達した場合など、そのまま保有し続けると利益が減ったり損失がでたりする恐れがあるので、元本保証型の商品にスイッチングすることで、利益確定したりできます。
iDeCoのデメリット
掛金は最低5,000円から
つみたてNISAのように、100円から積み立てができません。
しかし、月々数百円だと資産も増えませんし、運用してもなかなか増えません。
最低5,000円以上は納得できる金額だと思います。
資産が減ってしまう恐れがある
投資資産の価格変動や為替変動で、資産がマイナスになる恐れがあります。
原則60歳まで引き出せないので、途中の資産はあまり気にせず、愚直に毎月積み立てていきましょう。
引き出す5年ぐらい前から少しずつ、ポートフォリオの見直しやスイッチング、分配変更などして、受取時に多くの資産を残せるようにしていきましょう。
原則60歳まで引き出せない
メリットにも書きましたが、60歳にならないと引き出しできません。
しかも途中解約もできません。しかし、掛金の拠出を一時停止することは可能です。
手数料がかかる
- 加入時や移換時手数料に2,829円
- 口座管理手数料が毎月66円
- 事務手数料が毎月105円
- 運営管理手数料は金融機関によろ異なる。SBI証券は0円
毎月の掛金から引かれています。
掛金の変更は1年に1回だけ
月々の掛金の変更は1月~12月の間で一回だけなので、掛金の金額は慎重に考えた方が良いです。
おわりに
iDeCoを始めてから1年が過ぎました。
損益はつみたてNISAと共に良い成績でした。
しかし、景気には波があるので、数年後には大暴落などを体験することになると思います。
その波があっても、世界経済は上昇していくと信じているので、途中で諦めることなく、iDeCoの税制メリットを活用しながら資産形成をやっていこうと思います。